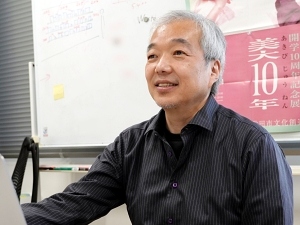辺境芸術編集会議 THE FINAL(1/2)/AKIBI plus 2017

秋田公立美術大学(秋田市新屋大川町)の岩井成昭教授のグループが、2015年から3年にわたり取り組んだアートプロジェクト「AKIBI plus(アキビプラス) ローカルメディアと協働するアートマネジメント人材育成事業」の事業報告を兼ねたトークイベント「辺境芸術編集会議 THE FINAL」が2月4日、同大学院棟で開かれた(関連記事)。県内4拠点で「地域アドバイザー」としてプロジェクトに取り組んだ以下の5人が事業報告とトークセッションを行った。
蛭間友里恵さん(秋田市、秋田公立美術大学大学院1年)、千葉尚志編集長(秋田市、秋田経済新聞)、猿田真さん(男鹿市)、柳澤龍さん(五城目町)永沢碧衣さん(横手市)。進行は岩井教授(以下、敬称略)。※撮影協力=草なぎ裕さん(同大学助手、なぎは弓へんに剪)

岩井「文化庁の『大学を活用した文化芸術推進事業』として、当大学と地域、ローカルメディアとの協働(関連記事)を考えながら、アートマネジメントのできる人材の育成などを目的に2015年から取り組んできました。初年度は、当大学が設ける『もう一つの学びの場』をテーマに、私たちがどのように地域と連携したらいいのか、どこで文化事業を始めたらいいのかなどについて、県内をリサーチしました。また、全国からマネジメントの専門家を招き、『アートマネジメントとは何なのか』について考えました(関連記事)。分かってきたことは、秋田には既に面白いアート・文化事業がたくさんあるということでした。これほど芳醇な土地の中で何かを新たに立ち上げるよりも、既に始まっている事業と連携して、当大学も学びながら協働できないかとの発想にいたりました。2年目は『仕掛ける人とのネットワーク』をテーマに、秋田・男鹿・五城目・角館(関連記事)の4カ所を『芸術価値創造拠点』に設け、拠点ごとに『地域アドバイザー』にリーダーシップをとってもらい、各拠点をリンクしながら活動を広げていきました(関連記事)。これらの成果を踏まえて2017年、横手も芸術価値創造拠点に加え、『辺境芸術編集会議』とのタイトルで展開しました」
アキビプラストーク&秋田芸術新聞編集部員ゼミナール/秋田

蛭間「6月の『キックオフ』から、東京の編集者を招いた『辺境の編集学』など、『アキビプラストーク』と題して5回のトークイベントを開きました。アートの視点と子育ての視点は同じなのではとの仮説の下、子育て中のアート関係者をゲストに招いた『子育て視点は芸術家の視点!?』では、子育ては他者との向き合うことや妊娠・出産を特権化しないことが重要との指摘を受けました。子どもの問いに親が応えることは哲学的でアートにおいても重要なテーマであることや、子育てに対するイメージや価値観、社会的規範を無批判に受け入れずに自由であるべきことなど、アートと子育てが重なる部分が多いことが分かりました。受講者から『子どものころから親しんでいたはずの音楽・絵画・芝居などが、アートという言葉に置き換えられることでよく分からないものに感じてしまう』との意見をもらいました。アート関係者がマジョリティーの環境では、アートに身近に接していない人々に対する暴力になってしまうとの意見です。(アート事業の)企画側は、このような意見があることを自覚することも必要だと思いました。
当プロジェクトでは、『辺境』がキーワードになっています(書籍『辺境芸術最前線 生き残るためのアートマネジメント』)。中央に対する辺境だとしても、自虐的に考えるのではなく辺境からメッセージを送ることができるのではないか、あるいは、中央を意識するのではなく辺境相互のリンクができるのではないかとの問題意識です。秋田を拠点に活動するバンド2組を招いた『辺境音楽の逆襲』では、ミュージシャンとして作品のクオリティーをしっかり追求することや、地域との関わり方は自身の問題として理解することの重要性などが話し合われました。異分野の価値観について話し合った『着想の交換』では、社会学や経済学を学んだ人がアート分野で活躍している事例などの紹介をゲストから受けながら、専門家に限らず関わることができる環境の有効性や(人的な)ネットワークを活用することの重要性などについて意見が交換されました」
辺境芸術編集会議(アキビプラストーク #1) 辺境の編集学(アキビプラストーク #2) 子育て視点は芸術家の視点!?(アキビプラストーク #3) 着想の交換~行動と批評と仲間探し(アキビプラストーク #4) 辺境音楽の逆襲(アキビプラストーク特別回)

千葉「架空の新聞『秋田芸術新聞』の編集部員の育成に取り組みました(秋田芸術新聞編集部員ゼミナール)。バーチャルですが、やることはリアルな講座です。人材の育成の観点から、アートマネジャーは、アーティストに寄り添うだけではなく、社会との接点を担う役割があるはずです。アーティストの取り組みをいかに伝えるのか。そのためには(アーティストの意図することの)翻訳と編集作業が必要になってきます。取材から執筆までさまざまなスキルが必要になってくるはずとの問題意識から企画しました。講座は、座学と実際に書いてもらった原稿を添削し、受講者同士で話し合う時間を設けるなどしながら実践的に進めました」
神々と生きる島を探る in 男鹿 準備講座&実践講座/男鹿

猿田「私は男鹿で『里山のカフェ ににぎ』を経営しています。前職が不動産関連の仕事だったことから、空き家や人口減、高齢化などの課題には身近に接していました。人口が減り続けるのは仕方ないとしても、どうしたら店に来てもらえるのか、地元の小中学校を残すためにはどうすればいいのかなどについて考えながら、地元で面白いことに取り組んでくれる人がいればとの思いで関わりました。
男鹿で芸術活動をするためには、地域をよく知ってもらう必要があることからフィールドワークに力を入れました。神や地形、私たちや地域のルーツ、歴史を知ることは非常に大事なことです。空き家や人口減少などの課題の解決のためには、地域に住んでもらうことが必要との思いから『空き家ツアー』を行ったり、今年度は影絵アーティストを招いた滞在型制作『アーティスト・イン・レジデンス』に取り組んだりしました。影絵作品の公演には120人以上のお客さんに集まっていただきました。私は芸術と地域を結ぶ人材を育成する事業のアドバイザーとの立場でしたが、成長できたのは私自身だったかもしれません。

文化庁の事業で公共のお金を使っていることなので、地域に対してどのように還元できるのかを意識して取り組みました。芸術分野における表現活動は、自分のお金を使うことのほか、税金を使うことや、そのほかの資金提供者がいて取り組むことなどがあるかと思います。また、暮らしの中から生まれてくる芸術に対する気持ち、地域の信仰や信じる力、神への感謝など無償の提供(による活動)もあります。なまはげの面を作ったり、祭りや行事で使う縄を編んだりすることは、誰かがお金を出して取り組むことではありません。生活ができることを神に感謝するものです。ライブ後に『皆さん働きましょう』と呼び掛けるアフリカのミュージシャンがいるのですが、祭りや行事は、普段働いて、自分たちが暮らしていけることに対して感謝するということ。芸術をやろうという気持ちより、働こうという気持ちが芸術や仕事、活動につながるのではと思います。男鹿に来て、また明日から頑張ろうという気持ちになってもらえればうれしいです。
ただ、私が望んだ課題はクリアできていません。当プロジェクトは地域にまいた種を芽吹かせる準備のための事業と解釈しています。一人ではできませんので、仲間探しや大学と関わるなど人とのつながりも必要です。いろんな人と交流する場として、いいプロジェクトでした。何をやるにも自分の家庭や生活があってのこと。それを大事にしながら関わっていくことができればと思っています」
今と昔を繋ぐアート/五城目

柳澤「東京から移住して5年になります。移住2年目のとき、築133年の茅葺屋根の古民家を拠点として仮想の村を作り、簡易性の農家民宿『シェアビレッジ』を立ち上げました(関連記事)。当プロジェクトでは2015年、五城目町を回るバスツアーを行ったのが最初です。私はアートの専門家ではないので悩みもありましたが、経験のある人が町内でギャラリーを始めたことから一緒に取り組みました。
プロジェクトに携わるにあたり、『辺境と芸術のシンポジウム』記事を繰り返し読みました。『文化は残すものではなく作るもの』『地域の文脈に寄り添うこと』『アートはいかに地方と向き合うか』…芸術はどのように地域と関わっていったらいいのだろうかと考える中、ゼロから考えた方がいいとの結論にたどりつきました。そして、地域を見て回りながら聞き書きすることを重視しました。当初は『町の人が町のことを好きになったらいいな』という願いを持っていました。(東京から移住した私に対して町の人々が)『どうしてこんな町に来たの?何もないでしょう』と言うのです。そこに卑下した思いがあるのだとすれば寂しい。『こんなに面白い町ではないか』との思いから、変な言い方ですが、町の人々を見返したいとの思いもありました。しかし、そのように考えると戦いの構図が生まれてしまいます。アートという言葉を使う人が特権的な立場に立ってしまうことがあるように、『町を好きになってほしい』と言うことは、町を好きであることが大事という価値観を押し付けることになるのではないかと。

町のことを知ろうとしたとき、町の歴史や経済、どんな産業があって、どのような人々がどんな仕事をしているのかということまでは容易に頭に浮かびます。しかし、それだけではない五城目があるのではないか、もっと町の魅力を見つけられるのではないかと2016年、『アートとソーシャルの交差点』と銘打ち、山形県の山伏(やまぶし)や写真家を招きました。町を回り、住民に会って聞いた言葉を約2000枚の付箋に書いて、地元のギャラリーで言葉の展覧会を開きました。これは町を見る行為だったと思います。また、五城目町史や秋田の方言の辞書などで勉強しました。しかし、町の人と話すと『(書籍に書かれていることを)そのまま信じてはいけない』との指摘を受けました。史実に基づいていなかったり、多くの解釈が加わったりしているからとのことです。見て読んでいるだけでは足りないことが分かりました。
自分たちでやることが必要と考え、3年目は体験をベースにしたプログラムに取り組みました。テーマは『今と昔をつなぐアート』(関連リンク)。今を調べることからも昔が見えてくるし、昔を調べれば今にどうつながっているのかが分かるのではないかと考えました。当町には、1895年生まれの農家で畠山鶴松(つるまつ)という人がいました。30年以上にわたり農家として体験してきたことをメモと落書きで書きつづった人です。このような一節が残されています。『俺の息子、孫まで笑ってもらうことも家内の幸福を得る一つのきっかけだろう。大いに笑って、喜んでもらうために書いてみた。末永く親父の書いたのを見て笑って和を得ることを望む』。ただただ家族が笑ってくれればいいのだとの一心で書かれたのが、この落書きでした。そこで、私たちも100年先の孫の世代に向けて、大いに笑ってもらえるような今日のことを落書きしてみようじゃないかと考えました。会場のギャラリーに模造紙を貼って、子どもたちにたくさんの落書きをしてもらいました。また、ポジティブなイメージを持ちがちな秋田弁ですが、地元の人からは『けなし言葉が多いよ』とも聞きました。そこで、秋田弁についても新しい理解を加えようと、町の人々が使うちょっと悪い言葉を集めた秋田弁の音声を記録して、昼ドラ風の秋田弁講座も企画しました。
私たちは町のことを全然知りません。歴史や経済のことだけ知っていても、知っていることにはならないのではないか。そして、私たち自身が新しい秋田像を作っていってもいいのではないかと考えています。町には、私たちの活動に関心を持ってくれる人も少なくありません。アートという言葉が敷居を高めているのなら、活動と人々や地域の全く新しい関係性を築いていければいいと思います。社会のためのアートという考え方ではなく、シンプルに『アートが好きだからやっている』という人々が来てくれるような町になる、好きだから取り組むということの先に、アートとの新しい関係ができてくるのではないでしょうか」
エリアブリュワー「地域醸造家の育成」/横手

永沢「昨年、当大学を卒業して、今は出身地の横手市に戻って会社に勤めながら作家活動に取り組んでいます(関連記事)。これまでは参加者として当プロジェクトに関わってきましたが、今回、初めて企画運営側に立ちました。
横手では『地域・発酵・アート・醸造家』の4つをキーワードに設け、人にとっていい働きをする、うまくいくことを作ったり起したりすることができる人を育てられないかと取り組みました(関連記事)。醸造や醸す、発酵させるという言葉はさまざまな場面で使われていますが、県内外からゲストを招き、『発酵している状況とは何か』を考えるシンポジウムを開きました。地域の因子を採取することや、因子の潜在力を見出して掛け合わせることで、どのように変容させられるのかなどについて考えました。

観光パンフレットや人々の会話などから言葉を選んだり、フィールドワークを行ったりして集めた地域の因子を、影響力と価値の大小を軸にグラフにまとめました。例えば、ナスとキュウリを刻んだものを玄関先にまくという十文字町の風習や、当地で作られる和紙などは、影響力は強くないが、価値や希少性は高いというように。有名な特産物や観光名物などよりもニッチなもの、希少で影響力が低いもの、すたれつつある文化などに注目が集まりました。参加者が『地域醸造家とは、変化と成長に向き合い、うまくいくための知恵やノウハウを持って触媒として動く人』などと定義し、グループごとに課題や因子を基に表現した作品を、ギャラリーではない市内3カ所を会場に展示しました(関連記事)。
一人では答えにたどり着きにくいですが、さまざまな人が交わることで日常とは異なる言葉が出てきます。古い文化も、専門家や職人の知識や技術が掛け合わさることからできたものと思います。地域のためというよりも、日常生活を楽しく生きたい思いですが、事業としてうまく成立させるためには、人々が掛け合わさることが必要です。そのためには、アートがもっと身近にあって、共有できる場所や機会が大切だと思います」⇒ 続きを読む